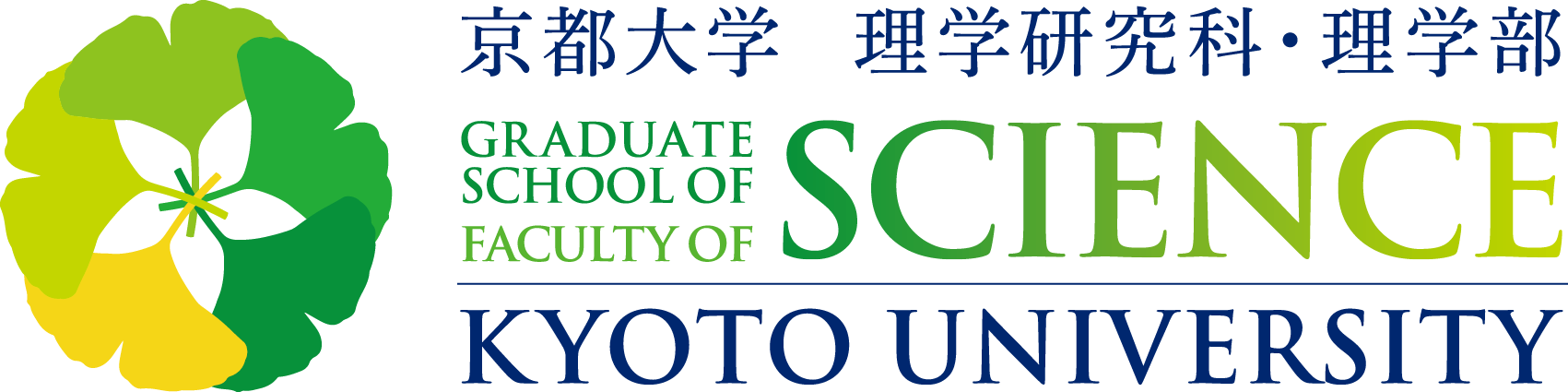生物科学専攻(生物物理学系)・准教授 寺川 剛

私は、分子動力学シミュレーション、1分子蛍光イメージング、ナノポアシーケンシングなどの手法を用いて、タンパク質の分子機構を研究しています。特にDNAの転写・複製・修復・高次構造形成に関わるタンパク質の分子機構に興味があり、それらの分子機構を物理法則にもとづいて理解したいと思っています。そのためには実験・理論・シミュレーションの密な協調が不可欠だと考えています。
大学の分子生物学の教科書をめくってみると、「真核生物のゲノムDNAはヒストンタンパク質に巻きついてヌクレオソームを形成しています。」と書いてあります。一方で、別のページには「ポリメラーゼというタンパク質は、ゲノムDNA上に沿って一方向に移動しながらDNAやRNAを合成します。」と書いてあります。それでは、ポリメラーゼがヌクレオソームと出会ってしまったら何が起きるのでしょうか?残念ながらその答えは、少なくとも私が読んだ教科書には書かれていませんでした。生物物理学や分子生物学はまだまだ発展途上な学問で、こうした素朴な疑問に自分たちで解答を見つけていく楽しさがたくさん残されています。
疑問が素朴だからといって、素朴な方法で解決できるとは限りません。我々は長年にわたって開発を続けてきた粗視化分子動力学シミュレーション手法[1]によって、ポリメラーゼとヌクレオソームの衝突に際してヌクレオソームが移動させられる瞬間を可視化し、「レーン・スイッチ機構」を見出しました[2](図1)。そして、最新のDNA配列決定法であるナノポアシーケンシングによって、その機構を検証しました[2]。現在では、より複雑なDNA複製装置複合体とヌクレオソームの衝突の研究も行っています[3]。これらは一例で、こういった素朴な疑問を解消しながら、DNAの転写・複製・修復・高次構造形成に関わるタンパク質の分子機構を少しでも明らかにできればと思い、研究を続けています。
[1] Takada, S., Kanada, R., Tan, C., Terakawa, T., Li, W., Kenzaki, H., 2015, Accounts of Chemical Research, 48, 3026
[2] Nagae, F., Brandani, G. B., Takada, S, Terakawa, T., 2021, Nucleic Acids Research, 49, 9066
[3] Nagae, F., Murayama, Y., Terakawa, T., Nature Communications, 15, 9485